|
|
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|
2 掲示板 |
|
掲示板 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
|
|
5月 6月 7月 8月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 3 4 |
|
|
|
|
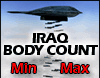 |


「Los Angeles 留学日記」
98-99年冬休み編3
(1999年1月9日〜)
1月9日(土)
篠原さんと一緒にLos Angeles Auto Showが行われているダウンタウンのコンベンションセンターへ。
一番気になっていたのはHONDAのニューモデル、S2000。
西海岸にはぴったりのスポーツコンバーチブル。
さすがに人気があるようで人垣ができていた。
これだけでなく、会場全体で目立っていたのがオープンカー。
市販車からコンセプトモデルまで様々なコンバーチブルが展示されていた。
東京モーターショーと一番違うのはキラキラの衣装を着たコンパニオンが各ブースにいないこと。
各社の広報スタッフがマイクを持ち、「I'm ○○○」と名乗ってから説明するのだ。
観客との質疑応答まであるのにはびっくりした。
会場内で唯一見かけたコンパニオンらしい女性がこの人。
どこかの改造パーツメーカーのブースで笑顔を振りまいていた。
もうひとつ面白かったのは実演販売のブースがいくつもあったこと。
テレビの通販番組そのままにカーワックスを売っていた。
夜はクリスマスに大好評だったキムチ鍋パーティー。
我が家に何と9人も集まって大にぎわい。
みんながテレビゲームや人生ゲームに夢中になっているその横で僕はこうしてホームページを更新しているのだった(笑)。
1月10日(日)
昨日は結局朝まで語り明かし、正午起床。
残り物のキムチ鍋でランチを済ませ、英会話学校の宿題をやっつける。
授業中に渡されたプリントの単語を使ってセンテンスを1つずつ作っていくというもので、これは楽勝。
1時間ほどでチョイノチョイだ。
そろそろ成績が発表されている頃だと思い出し、インターネットにアクセス。
CSUNの場合、Lookingglassという学生用のホームページで必要な情報はほぼ引き出せるようになっている。
授業や試験のスケジュールはもちろん、住所変更の届け出や成績もここにアクセスすれば一発なのだ。
IDナンバーと暗証番号をインプットすると、その結果は…
| Course Name | Title | Instr. | Units | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
Comp for Multimed | D Gotthoffer | 3 |
|
|
|
Corp Instr Mdia | J Stormes | 3 |
|
|
|
Extem Expo Wrtng | E Burow | 3 |
|
| GPA: |
|
| Total Units Earned: |
|
おおっ、パーフェクトだ!
ある程度期待していたとはいえ、こうして実際に目にするとやはり嬉しい。
夏学期のESLはクレジット(CR)・ノンクレジット(NC)評価だったから、「A」というグレードをもらったのは初めてのことになる。
僕の場合、卒業後の就職うんぬんはあまり考えていないので成績自体は気にならないけれど、今後トランスファーするかもしれないことを考えるとGPAがいいにこしたことはない。
ま、本当に大切なのは成績ではなく新しい知識をどれだけ習得したかということなんだよな。
来学期の科目登録は今週の水曜日。
よし、春もまた頑張ろう。
1月11日(月)
午前10時起床。
今日もGEOSの授業だ。
教室に入りあいさつもそこそこにJohn先生が切り出してきた本日最初の質問は「CultureとSocietyとCivilizationの違いは何だと思う?」。
おおっ、何というグッドタイミング!
「ちょうど今、『文明の衝突』という本を読んでいるところなんですよ」と答えると先生も身を乗り出してくる。
それから3時間はひたすら文明論議。
半分は本の受け売り、半分は僕自身の意見を一生懸命言葉を尽くして説明する。
相変わらず文法的にはグチャグチャだったりもするが、不適切な表現が出るたびにその場で正しい表現を教えてくれるので会話はスムーズ。
意外なことに、テーマが堅いにもかかわらず先生の英語はほとんど素直に理解できた。
もちろん、僕のレベルに合わせて易しい語彙を選んでくれているのだろうけれど、やはり興味を持っている分野の話は素直に耳に入ってくるのだと思う。
興味深かったのはユーゴスラビアの話題になったとき。
先生の口からユーゴスラビアの地名や政治家の名前がポンポン出てくるのだ。
これは先生が特別ユーゴスラビアについて詳しいからなのだろうか?
いや、違う。
きっとアメリカ人(あるいは欧米人)にとってこの問題は僕たち日本人にとってよりずっと身近な問題なのだ。
残念ながら新聞を斜め読みしたくらいの知識しかない僕は知らない名前が出てくるたびに説明を求めなければならなかった。
もうひとつ面白かったのはギリシア文明について話が及んだ時だ。
先生が「どうして哲学はギリシアで生まれたと思う?」と聞いてきた。
僕の仮説は「奴隷制があったから」。
「生活の雑事を奴隷に任せることによって富裕層には時間的余裕ができたはずだ。ヒマができると自分の存在について深く考えてしまうのが人間というもので、それが哲学のルーツになったに違いない」と答えた。
これに対して先生の仮説は「ギリシアでは早くから航海術が発達したから」。
「海を渡って他の文明と接触する機会が多かったギリシア人は自分たちと異なる価値観にぶつかったはずだ。その結果、物事を普遍的に説明できる哲学を生み出す必要性があったのではないか」
う〜む、なかなか説得力のある説じゃないか。
とすると、海を渡ってアメリカ文化と接触している僕は哲学に少し近づいているというわけか(笑)?
こんな調子で気がついたら予定時間を20分もオーバーするほど会話に熱中していた。
いやぁ、楽しいなぁ。
こんなアカデミックな議論を英語でしている自分に酔ってしまいそうだ(笑)。
さては、こうやって僕に自信をつけさせようという魂胆に違いない(笑)。
帰り際に「英語を学びたい日本人と日本語を学びたいアメリカ人が交流する無料のLanguage Exchangeプログラムがどこかにあるという噂を聞いたんですが、知ってますか?」と聞いたら「確かウチに資料があったと思うな。次回の授業までに調べておいてあげるよ」というお答え。
おおっ、これは力強い。
さすが餅は餅屋だ。
期待してしまおう。
帰ってきたら先学期のクラスメイトTheoからメールが届いていた。
「今日からウチのインターネットはケーブルモデム経由になったのさ! メチャクチャ早くて快適だぜ!」という自慢だ。
う、うらやましい…。
彼のアパートに入っているMedia-Oneというケーブルテレビ会社はインターネットアクセスのサービスも提供しているのだ。
テレビと合わせて1ヶ月の料金は$50以下だという。
残念ながら僕のアパートに入っているCentury Communicationsは同様のサービスをやっていない。
もしケーブルモデムで快適にアクセスできるのなら思い切って申し込んじゃうのになぁ。
「Joeとも連絡取ったんだけどさ、3人で会って何かやりたいなって言ってるんだ」
おっ、これは話がいい方向へ転がりそうだぞ。
ネイティブの友人が欲しいって書いたこのホームページを読んだのか?
まさかね。
1月12日(火)
ようやく「文明の衝突」を読了した。
ハーバード大学の教授で戦略論の専門家である著者サミュエル・ハンチントンは世界を西欧、中国、日本、イスラム、ヒンドゥー、スラブ、ラテンアメリカ、アフリカと8つの文明に分類している。
冷戦によるイデオロギー対立がなくなると人々は自らのアイデンティティーの根拠を文明に求めるようになり、21世紀前半の世界には文明間の紛争が浮上してくるというのが彼の主張だ。
その上で「世界にただ一つリベラルな民主主義に基づいた普遍的な文明」が生まれつつあるというのは西欧の思い上がりであって、他の文明圏から見ればそれは帝国主義に映るという。
今後の世界では中国文明とイスラム文明の勢力が台頭し「西欧対非西欧」という対立の構図になるというのである。
世界中で議論を巻き起こしたベストセラーだけあって興味深く読んだ。
説の真偽は今後の歴史が証明していくとして、僕も身近なところで少し考えさせられた。
それは留学生のアメリカに対する接し方である。
日本人であるか否かに関わらず、その態度は大きく2つに分けられるような気がするのだ。
1つはアメリカ順応型。
アメリカ的な自由主義、競争主義、個人主義、あるいはポップカルチャーを優れたものと考え、極端な場合、自国の文化を否定さえしてしまう人。
よく言えば順応性が高く環境に溶け込むのがうまいとも言える。
もう1つはアメリカ否定型。
アメリカから学ぶのはごく一部の限られた分野の知識のみで、その他の部分ではかたくなに自国の文化を貫き通す人。
保守的で頑固だ。
Coffee Hourなど僕の少ない交流から言うと、前者は中学・高校など思春期からアメリカで生活している留学生に多く、中国人やイスラム系の留学生には後者が多いような気がする。
日本人には順応型が多いだろうか。
ま、もっともこれは留学生に限ったことではない。
母国語のみの看板がチャイナタウンやコリアタウンに多いのにリトルトーキョーではほとんど見かけないのもそういうことなんだろう。
では、僕はどうだろう?
アメリカ的な自由や個人主義を心地よく感じることは確かに多い。
結果の平等ばかりに重きが置かれる日本のシステムもどうにかならんもんかと思う。
が、一方で日本の美点も改めて思い知らされる。
謙虚さや慎み深さ、あるいは礼儀正しさに欠けるアメリカ人には違和感を覚えることが多いし、英語では表現しきれない日本語のワビサビが僕の中にすっかり根付いている。
実際には時と場合によって順応型と否定型の間で大きく揺れ動くのが本当のところだ。
たとえ今後何年アメリカで生活しても100%順応することはないだろうし、したくもない。
かといって100%否定するのも何か違う。
日本とアメリカの「いいとこ取り」がしたいなんていう虫のいいことを考えているのだけれど。
いずれにしても異国で生活するというのは折に触れてアイデンティティーの確認を迫られることだ。
やがて卒業して帰国する頃、この日記を読む僕はどんな僕になっているだろうか。
楽しみでもあり、また不安でもある。
1月13日(水)
午前10時起床でGEOSへ。
John先生の第一声は「今日はHiroのためにProverbをたくさん用意してきたよ」。
慌てて辞書で「proverb」を調べると「ことわざ・金言」とある。
「There is no use crying over spilt milk」とかだったら駿台の700選で覚えたもんね、なんて思っていたらもうちょっとハイレベルな(?)やつだった。
第1問。
「Success is not a destination, it's a journey, it's the direction in which you are traveling.」
直訳すれば「成功は目的地ではない。それは旅であり、旅する方角である」となる。
僕が「成功は単なる中間地点でしかないから、さらに次に向かって努力を続けなければいけない」という解釈を説明すると先生は「オー、Hiroは頑張りすぎだよ」と笑う。
正しくは「成功することだけにとらわれてはいけない。そこまでのプロセスを楽しむべきだ」という意味なんだと。
ふ〜ん。
第2問。
「A dime and $20 gold piece have the same value if they are corroding at the bottom of the ocean」
直訳は「海底で腐食していたら10セント硬貨も20ドル金塊も価値は同じだ」。
僕の解釈は「自分の手に入っていないものは高かろうが安かろうが価値は変わらない」。
つまり「とらぬタヌキの皮算用」みたいな意味なんだろうと思ったのだ。
が、またもや不正解。
正しい意味は「せっかくの才能も眠らせていては意味がない」。
何だよ、今度は「頑張って努力しろ」ってことかい。
もちろん、ことわざ自体を学ぶのも意味があるが、僕にとっては自分の解釈をいかに正確に相手に伝えるかという表現の訓練になる。
いつものように間違った表現にはすかさず先生のチェックが入るのだ。
それにしても毎回手を変え品を変えいろんな方法があるもんだ。
「金曜日はHiroが日本の大学で専攻していた政治について議論しよう」と先生は言う。
テーマが何であれ、今は自分の意見を伝える訓練になるのならウェルカムだ。
アパートに帰ってきて来学期の科目登録。
例によって電話を使ったTouch Tone Registrationというシステムだ。
今回、僕が登録したのは2科目。
どちらも先学期お世話になったDoug Gotthoffer教授のクラスだ。
まずはRTVF 315 New Direction in Electronic Media System (電子メディアシステムの新しい動向)
カタログには「プログラムの制作・普及のための電子メディアシステム研究。制作側、規制側と社会全体の関連性について」とある。
日本ではインターネットや伝言ダイヤルを使った薬物事件が起きて改めて新しいメディアへの規制が強まりそうだけれど、表現の自由が大事にされているここアメリカではこの問題にどう対処していこうとしているのか、きっとそのあたりのことを勉強するのだろう。
教授によるとMidtermに4〜5ページ、Finalに20ページのレポートが課されるとのこと。
このFinalが来学期最大の難関になるのは間違いない。
もう1つはRTVF 461 Interactive Multimedia Development (双方向マルチメディアの展開)
これは先学期に取ったRTVF 361 Computer Fundamentals for Multimedia (マルチメディアのためのコンピュータ概論)の上級編。
教授によればJava ScriptやLingoを使った双方向メディアの制作と理論分析が主になるとのこと。
これは楽しみながらできそうだ。
授業で学んだテクニックはこのホームページにもぜひ応用したいと思う。
Prerequisiteが壁になって大学院のクラスが取れないという問題はまだ未解決。
何人かの教授に「Prerequisiteを外してくれないか」というメールを送ったのだけれどいまだになしのつぶてなのだ。
もう一度しつこく送っておこうと思う。
あっ、John先生にLanguage Exchangeのことを聞くのをすっかり忘れてた。
金曜日には忘れずに聞かなくちゃ。
1月15日(金)
午前10時起床でGEOSへ。
今日最初の質問は「来週の月曜日は何の日だか知ってるかい?」
もちろん知っている。
Martin Luther King Jr. Dayだ。
CSUNの英会話クラスでもそうだが、先生はタイムリーな祝日を話題のきっかけに持ち出すことが多い。
ハロウィンしかり、サンクスギビングしかり。
英語を学ぶということはこうやってごく自然にアメリカ文化や歴史の知識を吸収していくことにつながっていくのだ。
人種差別が行われていた時代背景やそれに対するMartin Luther King Jr.とマルコムXのアプローチの違いなど、どこかで読んで脳みその片隅に残っていた知識が意外に役に立つ。
John先生のいいところはこういう話題を単なる知識の伝達で終わらせないことだ。
「それから30年以上経ったけど人種差別はなくなったと思うかい?」
「なくすためにはどうすればいいと思う?」
「差別をなくすための法律が逆差別を生んでいると言う人がいるけれど、そう思うかい?」
話題はさらに移民の歴史に広がり、「アメリカの移民政策についてどう思う?」
「日本は移民をもっと受け入れるべきだと思うかい?」
こうした意見の分かれるテーマを投げかけ、僕と正面から議論しようとする。
英語については先生と生徒だが、議論の中身についてはフィフティーフィフティーだ。
先生も議論自体を楽しんでいるように思える。
帰り際にLanguage Exchangeについて質問。
John先生によると、このプログラムは毎週月曜日から金曜日までの毎日午後6時から9時までリトルトーキョーのJACCC(日米文化会館)で行われているとのこと。
人数は15人から30人(大ざっぱに言うと日本人6割アメリカ人4割)くらいだという。
タダで英語を学べるならこんなにオイシイ話はない。
近いうちに機会を見つけて行ってみようと思う。
夜、MikioさんとAtsukoちゃんから食事のお誘い。
殺し文句は「宇宙一旨いハンバーガーを食べに行きませんか?」
なんでもZAGAT(アメリカの権威あるレストランガイド。「ミシュラン」みたいなもの)最新版でそう紹介されている店を見つけたというのだ。
さすがはグルメのMikioさん、1997年版しか載っていないインターネットより情報が早い。
こちらがその「宇宙一旨いハンバーガー」の店Apple Pan。
店内は全席カウンターで、アメリカ映画によく出てくる“街道沿いのダイナー”みたいな雰囲気だ。
ウチから車でたった5分のところにこんな店があるなんて知らなかった。
はたして「宇宙一旨いハンバーガー」の味は…!?
近日中に「L.A.いい店やれる店」のコーナーにアップしますので乞うご期待!
1月16日(土)
午後2時起床(おうおう、いつまで寝てやがるんだ)。
次のGEOSは来週の水曜日だし、宿題もないから実質的に4連休。
もう、めちゃくちゃヒマなのだ。
かと言ってどこかに出かける金はなく、アパートにこもってテレビと読書三昧ということになる。
「あなたはもう幻想の女しか抱けない」速水由紀子(筑摩書房)読了。
著者は東電OL殺人事件、中学生ナイフ事件、援助交際ブームなどの原因を家族の関係性に求めて分析している。
なかなか説得力があるような気もする一方、何か物足りないような気がするのは何なのだろう。
異国で生活していてしみじみ感じるのは「人間はコミュニケーションなしには生きられない動物なんだ」ということだ。
いろいろな場面ですぐ不安や恐怖が頭をもたげてくるのは英語が不自由で周りの人とのコミュニケーションが不完全だということが大きな理由だと思う。
他人の言っていることが分からなかったり自分の言いたいことを充分に伝えられないというのは本当につらい。
念のために言っておくと、これはケンカするとか理解し合うとかいう以前の段階。
ケンカだって一種のコミュニケーションだから。
幸いなことに僕はナイフを持って暴発したり援助交際に走ったりはしない(援助してもらいたいくらいっす(笑))けれど、彼らはこの疑心暗鬼の延長線上にいるんじゃないかなと何となく感じるのだ。
うまく説明することはできないけれど。
夕方、篠原さんと「Inside Edition」翻訳作業。
今週はクリントン弾劾関連の特番でオンエアが数本飛ばされていた。
1月17日(日)
午後4時起床(おい、いいのか、そんなことで)。
ゆるゆるとテレビを見ながら食事をとり、Kanaちゃんから借りてきた「詳説世界史」(山川出版社)を読み始める。
早い話が高校の世界史教科書。
いわゆる“山川の世界史”だ。
僕が高校を卒業してから10年以上。
あの頃は表紙すら見たくなかった教科書を今になってこんなに読みたくなるとは思わなかった。
そう言えばフライデー事件で謹慎中のビートたけしさんが小学校から高校までの全教科書を読破したという話を聞いたことがあるが、その気持ちはよく分かる。
同じ教科書を読んでも当時と今とでは理解度が段違いなのだ。
高校時代には単に暗記すべき記号でしかなかった言葉たちが現代とつながる生きたキーワードとして素直に脳みその中に入ってくる。
が一方で、教科書は読み物としては最低だと思う。
ヘブライ人はもと遊牧民であったが、前1500年頃パレスティナに定住し、一部はエジプトに移住した。
しかし、そこでは新王国の圧政に耐えかね、モーゼに率いられてパレスティナに脱出した(出エジプト)。
前1000年ごろヘブライ人の国家は王政となり、ダヴィデ王とその子ソロモン王のもとに栄えたが、
ソロモン王の死後、国は北のイスラエルと南のユダに分裂した。
このころ何人かの預言者があらわれて、人々の堕落をいましめ、民族の結束を説いたが、
そのかいもなくイスラエルはアッシリアに滅ぼされ(前722年)、
ユダも新バビロニアに征服されて、住民の大部分が前586年バビロンに連れ去られた(バビロン捕囚)。
(「詳説世界史」24ぺージ)
これを読んでワクワクしたり歴史の面白さに目覚める高校生がどのくらいいると言うのだろう。
公正中立でなければならない(僕はそもそもそれが不可能だと思うが)という教科書の建前があるにしてもつまらなすぎる。
「The Prince of Egypt」でも見た方がよっぽど理解が深まるに違いない。
こんな教科書を題材に授業を行わなきゃならない先生も気の毒だ。
聞いた話だが、Santa Monica Collegeの近現代史のクラスで第二次世界大戦についての授業の後、「自分が当時の日本人になったつもりでアメリカ人の友だちに手紙を書きなさい」という試験があったという。
どうせ歴史を学ぶのならそういう方が楽しいよなぁ、と僕は思うのだ。
1月18日(月)
Martin Luther King Jr. Dayのため学校は休み。
ということで午前中から篠原さんとKanaちゃんが我が家に来る。
篠原さんは僕のプリンタを使って映画のクラスのレポートを印刷、Kanaちゃんは写真のクラスの撮影だ。
一通り終わったところで久しぶりにSanta Monica Placeへ。
ふらふらとサードプロムナードを歩いていたら何と舞妓さんを発見!
どうしてこんなところに…と思ったら、京都の観光協会か何かがプロモーションを行っていたのだ。
満面の笑みで通行人の注目を集めていた舞妓さん、明らかに日本人だと分かる僕らにもしっかり絵ハガキとティッシュを配ってくれたのだった。










