|
|
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|
2 掲示板 |
|
掲示板 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
|
|
5月 6月 7月 8月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 3 4 |
|
|
|
|
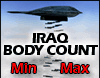 |


「Los Angeles 留学日記」
大学院99年春3
(1999年2月20日〜)
正午起床。
カゴいっぱいにたまった洗濯物を抱えてランドリーに行こうと部屋を出ると、空が青いこと、青いこと。
しかも風はさわやかに吹き渡り、2月だというのにL.A.はもうすっかり春めいている。
あ〜、遊びに行きたいっ!
どこか海の見えるテラスでお茶でもいただきながら、ゆるりと読書してのんびりしたいぞ、コノヤロー!
と思わずにはいられないほどの天気なのだ。
がしかし、僕には山盛りの宿題がある。
同じ読書でも狭い部屋の中でひたすら辞書を引きながらのリーディングだ。
「アメリカのテレビの1カットは平均3.5秒。視聴者の感覚に訴えるメディアである」
「大統領選挙であれ殺人事件であれ、テレビの手にかかれば全てはエンタテイメントになる」
賛成。
僕もそう思う。
ただ、著者はこれによって現代の文化から「考える」傾向がなくなる懸念を示しているけれど、僕はそうは思わない。
視聴者はそんなにバカじゃない。
一日中テレビを見ているだけじゃないのだ。
どんなにテレビが普及してもラジオも新聞も本も絶対になくならない。
僕らは多様化したメディアの選択肢から目的に応じて適切なものを自由に選べばいいだけだ。
ただし、もはやメディアを黙って信頼する時代ではないと思う。
情報の受け手側がメディアに常に疑いを持って接し、真偽を見極めるリテラシーが必要だ。
その無言のプレッシャーが送り手にいい意味での緊張感をもたらし、情報の質を高めることにつながると思う。
というわけで、宿題となっていた15ページはなんとか読了。
これからインターネットでスピーチのネタを調べなければ。
笹生さんから阪神淡路大震災のVTRが見つかったとのメール。
本当にありがたいと思う。
昨夜は地震についての資料集めで結局、一晩中ネットサーフィン。
関東大震災や阪神淡路大震災、防災訓練やボランティアについての資料がけっこう集まった。
基礎データについては大学や省庁のホームページを中心に調べたのだが、お役所の文章ってどうしてこんなに読みにくいんだろう。
例えば、国土庁の「平成8年度総合防災訓練大綱について」というページにこんな一節がある。
防災関係機関による情報の収集・伝達及び広報訓練
防災関係機関による情報の混乱防止に配慮した、警戒宣言時及び災害時における迅速・的確な災害関係情報の収集・伝達・広報訓練
防災関係機関相互間及び防災関係機関と住民等との間における情報の収集・伝達・広報訓練
災害発生後の余震、降雨等による土砂災害及び建物の倒壊、公共施設の破損など二次災害防止のための点検、避難誘導訓練及び住民の安全確保のための広報訓練
非常通信協議会構成員相互間における中央防災無線等各種の通信網を活用した情報伝達訓練及びパソコンネットワ−ク等を活用した情報伝達訓練
うわぁ、めちゃくちゃ漢字が多い!
オンラインで読むなんてとんでもない。
プリントアウトしたって読むのに一苦労だ。
もちろん情報を公開しているというのは意義があることだけれど、もしかしたら読む人のことなんてちっとも考えてないんじゃないだろうか?
とりあえず資料は集まったけれど、これを整理して7〜10分のスピーチにまとめるには一苦労ありそうだ。
とういわけで、ひとまず地震ネタから逃避してDirectorとLingoの使い方をマニュアル本片手に勉強。
コンピュータの本もお役所言葉とは違った意味で読みにくかったりするのだけれど(笑)。
まだまだやることはいっぱい。
笹生さんから阪神大震災のVTRが見つかったとのメール。
本当にありがたいと思う。
正午起床。
Theoから「先週撮影したRTVF341のミニドラマに照明のミスがあったので再撮影したい。協力してくれ」というメールが届いていた。
ご丁寧に「Hiroの演技はみんなにバカウケだったよ」と付け加えて。
本当はやらなきゃいけないことがたくさんあるから断りたいところだけど、僕がいないと他のシーンも全部最初から撮影しなきゃいけないいもんな。
しょうがない、また笑いをとってやるか(笑)。
昼食の後、SPICEのスピーチ原稿。
原稿というよりは英語と日本語が半分半分のラフな構成案という感じ。
水曜日のリハーサルの後、細かい詰めをやろうと開き直ったら気が楽になった。
いざとなったら笹生さんが送ってくれる阪神大震災のVTRをずっと流してやれ(笑)。
続いてLingoをマニュアル本で勉強。
いよいよ本格的なプログラムの部分に入る。
実際にプログラムを書いていて思ったのだけれど、これってやっぱり英語が母国語の人間の方が圧倒的に有利だよなぁ。
「よし、完璧だ!」と、書き上げたプログラムを走らせても、たった1カ所スペルミスがあるだけで止まってしまったりする。
まったく、こんなところでまで英語に苦しめられるとは。
技術大国ニッポンの偉い方、どうぞ日本語でスラスラ書けるプログラム言語を開発して下さいな。
先日注文した小切手帳が届いていた。
とりあえずは騙されなかったということで一安心。
もちろん、実際に使ってみなきゃ分からないけれど。
結局、この週末はほとんど部屋から出なかったけれど、やるべきことの8割方はできただろうか。
それにしてもずっと机に向かっているのには飽きたよ、もう。
午前9時起床で学校へ。
今日のL.A.は快晴!
しかも日中はTシャツ1枚で十分なほど暖かい。
きっと25度くらいあったに違いない。
クラスメイトに「すっかり春だね」と言うと「L.A.に冬なんてあったっけ(笑)?」という返事が返ってきた。
僕はこの気候がけっこう気に入っている。
というわけでNew Direction in Electronic Mediaの教室へ。
前半はテキストの内容をベースにしたディスカッション。
テーマは「テレビというメディアは全ての内容をエンタテイメントにしてしまうバイアスがかかっているか?」。
教授の進行に沿ってクラスメイトが次々に手を挙げて発言していく。
と言っても全員が積極的というわけではなく、25人中10人くらいが何度も何度も発言するのだ。
もちろん、僕は残りの15人側(悲)。
議論自体は興味深い(半分くらいしか聞き取れてないけれど)のだが、例によって前の発言を理解して「あっ、これを言いたい!」と思った瞬間にトピックは次へと進んでいる。
そんな瞬間が3回はあっただろうか。
無理すれば割り込めなくはないのだろうけれど、「話の流れを壊しちゃいけないよなぁ」という変な遠慮が災いして結局、一度も発言できず。
ホント、この授業に出るたびに情けない気持ちに打ちのめされてしまう。
後半はいよいよ初のディベート。
「資本主義経済の本質を考えた場合、我々の消費をあおるテレビの発達は不可避だった」というテーマについてKellyが賛成、Natalieが反対の立場でプレゼンテーションする。
事前に2人の書いてきたペーパーが配られるので要旨は分かる(といっても目を通す時間は数分間だからごく大ざっぱな大意だけ)のだが、いざスピーチとなると耳がついていかない。
聞き取れなければ当然議論に参加することもできず、今日の僕のParticipationはゼロだ。
授業の後、MakiちゃんとMarikoちゃんに聞いたら、2人はこの議論がほぼ聞き取れているという。
これを聞いてますます落ち込んでしまうのであった。
気を取り直してミニドラマの撮影。
照明のミスで影が出てしまったシーンだけということで気楽にやる。
僕はたくさん宿題を出すイヤな教授という役どころ。
カッとなってナイフを持ち出した学生を冷静に拳銃で撃つというとんでもない教授なのだ。
拳銃はもちろんモデルガン。
だけど、これが本物でもちっとも不思議じゃないんだよな、アメリカっていう国は。
最後にみんなで記念撮影。
「編集が済んだらコピーテープをあげるよ」という申し出に、つい「じゃあ、そうしたらそれを僕のホームページに載せるよ」なんて返事をしてしまった。
やばい、どこかにサーバスペースを確保しなきゃ。
楽しかったよ。
みんな、どうもありがとう。
午前8時起床。
SPICEスピーチのリハーサルのため学校へ。
ここのところ毎晩3時4時まで勉強しているので体力的にちょっとつらい。
授業がないのにいつもより早起きなんて、どないなっとんねん。
International Student OfficeにRoopaさんを訪ねる。
一緒にリハーサルをやるはずだったセバスチャンは寝坊で欠席。
どないなっとんねん、もう(笑)。
「本番と同じようにやってみて」と言われ、ラフ構成に沿って一通りしゃべってみるがなかなか思ったように言葉が出てこない。
阪神大震災の日付や被災者の数などメモを見ながらしゃべっているとRoopaさんがすかさず「読んでちゃダメ!」と突っ込んでくる。
日本語ならチラッと目をやるだけですぐ視線を元に戻せるが、英語ではそうはいかない。
けっこう大変だぞ、こりゃ。
結局、金曜日にもう一度リハーサルをすることになってしまった。
今日の反省を元に僕が考えたのは「スクリーン誘導作戦」。
本番ではオーバーヘッドプロジェクターを使うことができるので、写真やデータはすべてここに入れ込み、スピーチはその補足説明に回すのだ。
スクリーンに具体的な数字が出ていればスピーチでは「many people」で済む。
困ったら「like this」と写真を指せばいい。
要するに細かい内容を覚えて行かなくてもスクリーンに映し出されたものを見たとおりに説明していけばスピーチになってしまうという見事な作戦だ(苦笑)。
もちろんそのためには魅力的な写真やデータを用意しなければならないけれど。
リハーサルはたった30分で終わってしまったのだが、せっかく学校へ来たのだからと図書館で勉強することにした。
CSUNには実に立派な図書館がある。
僕は今までほとんど利用したことがなかったのだが、これがなかなかいい。
1人分に区切られた机は広く、イスもなかなかの座り心地。
これなら落ち着いて勉強できる。
というわけで、辞書を引きながら6時間かけて18ページのゲーム企画書を読破。
もう、ヘロヘロだぁ。
アパートに帰ると笹生さんから阪神大震災のVTRが届いていた。
さっそくチェックしてみると中身もバッチリ!
あぁ、助かる。
これでスピーチもなんとかなるだろう。
日本の某制作会社から電話で企画書の依頼。
大変お世話になっている筋だけにいいかげんな仕事はできない。
しかも、けっこう面白そうな話なのだ。
無理やり締切を週明けにしてもらい、ありがたく引き受けさせてもらう。
ああ、当分のんびりはできないのかなぁ。
午前7時半起床で学校へ。
授業の前にオフィスアワーのGotthoffer教授に会っていくつか相談したいことがあったのだ。
これが教授のオフィス。
「こんなにちらかっているところを撮るのかい?」と言いながらしっかりポーズを取ってくれる教授が僕は好きだ(笑)。
1つ目の相談はもちろんNew Direction in Electronic Mediaのディスカッションについて。
「言いたいことはあるのだけれどタイミングを逸してしまってなかなか発言できない」と僕の情けない実状を説明すると、「気にすることはないよ。ディスカッションなんていうのはそもそも話題が行ったり来たりするものだ。Hiroが話の流れを戻したとしても誰もイヤな顔はしないと思うよ」と暖かいお言葉。
「先学期の僕の授業には聴覚障害の生徒が口述筆記のヘルパーと一緒に参加していたんだけど、そのヘルパーは書くのが追いつかなくなると『Stop!』と言ってたよ。Hiroも聞き取れないことがあったらいつでも遠慮しないで『Stop!』と言えばいいんだ」
実際にそうできるかどうかは別にしてずいぶん気が楽になった。
さらに「話の途中で割り込むのが難しいのなら、授業の最初にキミを指名することにしよう。次の授業でさっそくやるから自分の考えをまとめておきなさい」とまで言ってくれた。
ああ、優しい人だなぁ。
実のところ、留学生だからといって特別扱いされるのは本意じゃないのだけれど、教授の優しさはありがたく受け止めさせてもらおうと思う。
2つ目の相談は来学期以降の科目について。
学部長の「来学期はマルチメディア関係の授業を増やすつもりだ」という発言について詳しく教えてもらおうと思ったのだ。
なんと言ってもGotthoffer教授はRTVF学部ナンバーワンのマルチメディア教授だから。
彼の説明によると確かに数科目が新設されるとのこと。
ただし、大学院の授業にこの傾向が反映されるまでにはしばらく時間がかかるかもしれないという。
「USCのカタログを入手して研究しているんですが…」と僕が言うと、「大学院でマルチメディアをやるのならUSCの方がいいよ。役に立つかどうか分からないけれど知り合いの教授を紹介してあげよう」とメールアドレスを書いてくれた。
しかも「出願の時に必要なら僕が推薦状を書いてあげるよ」とまで。
う〜む、GPAが足りないのは承知だけれど、ここまでしてくれるのに知らんぷりするのは申し訳が立たない。
近いうちにメールで連絡を取ってみようと思う。
午前11時起床。
睡眠時間8時間。
久しぶりによく寝た。
目覚めもスッキリ、気分爽快。
やっぱりこうでなくっちゃね。
今日は集に一度のCoffee Hour。
僕が先学期取っていたComputer Fundamentals for Multimediaを取っているJinkyuからレポートを見せてくれと頼まれていたので持っていくと「おおっ、これでバッチリだ!」とオーバーアクションで喜んでくれた。
こんなんでお役に立つならいつでもどうぞ。
困ったときはお互い様だよね。
今日、一番面白かったのはグレゴリーというアメリカ人の話。
日本にも留学したことがあり、現在の彼女も日本人という日本通の彼が僕にこんな質問をしてきた。
「日本人の女の子はどうしてみんな肩がこってるんだい? 今までに何人かの日本人とつき合ったけれど、例外なく全員が僕に『マッサージしてくれ』って頼むんだ。アメリカ人からそんなことを頼まれたことは一度もないのに…」
よく聞いてみると、どうやらアメリカ人は肩がこらないらしい。
慢性肩こりの僕には彼女たちの気持ちがよく分かるけれど、彼にはそれが理解不能なのだ。
ちなみに和英辞典で「肩こり」を引いてみると、
stiff shoulders (★英米人には肩凝りはあまりないという. したがってこの言葉もあまり用いられない).
と出ている。
やはり彼らは肩がこらないのだ。
どうしてなんだろう?
食習慣や生活様式が違うのか、それとも筋肉の質が違うのか?
この問題を研究したらもしかして肩こりの抜本的な解消法が分かったりするんじゃないだろうか?
今度他の国の留学生たちにも聞いてみよう。
SPICEスピーチのリハーサルをやろうとRoopaさんのところに行ったら「あれっ、こないだやったからもういいわよ」との返事。
おいおい、今日2回目をやろうって言ってたじゃない。
そのために昨日一生懸命スライドを作ったのに…。
ま、あとはぶっつけ本番でどうにかなるだろうと気楽に考えることにした。
アパートに帰ってたまっていた新聞を1週間分まとめてのんびり読む。
今週はホントに忙しかったからなぁ。
とはいえ、のんびりはしていられない。
今週末の“やらねばリスト”は…
1 2000年開局BS放送編成企画書(週明けまで)
2 New Direction in Electronic Mediaテキスト読み55ページ(火曜日まで)
3 Computer for New Mediaテキスト読み40ページ(木曜日まで)
ふぅ、この週末はちょっと出かける用事もあるし、けっこう大変だ。
でも先週よりはちょっとましかな。
うん、だから今日は寝ちゃおう(笑)。
午前11時起床。
篠原さんとその映画学科の同級生Tomoyukiと3人でSanta Monica Civic Auditoriumで開かれている「Post/LA Expo」へ。
これはデジタル技術を使ったポストプロダクションの展示会。
だけど、ハード音痴の僕は展示を見ても「とにかく技術はすごいことになっている」ということしか分からなかった(笑)。
それより面白かったのは会場内で行われていたコンファレンス。
最新技術を使って作られた映像が次々にモニターに映されていくのだ。
ほとんどはCGそのもののプレゼンテーションだったが、中にはこんなものがあった。
とある映画のロケ現場。
「カ〜ット!」と監督が叫ぶやいなや、そのシーンの映像が回線を通じて編集室に送られる。
待ちかまえていた編集マンはその前後のシーンをつなぎ合わせ、ボタン1つで再びロケ現場に送り返す。
モニターの前で待ちかまえていた監督は編集された映像を見て自分のイメージに合うかどうかを確認できるのだ。
う〜ん。
確かにこういう技術があると撮影が効率的に進むのかもしれないけれど、なんだか違和感もあるよなぁ。
そんなこと言ってる僕は技術の進歩に置いていかれちゃうかな(笑)。
ま、いずれにしても作り手が何を表現したいのかが一番大切だという点は変わらないんだよな。
会場をフラフラしていたら僕のCD-ROMでグラフィックを担当して下さる金子さんとバッタリ。
やっぱり興味を持っているところは同じなんだなぁ、と少し嬉しくなった。
帰りにサンタモニカのプロムナードを散策してLight Houseという日本食レストランで食事。
ランチタイムは1人$9.95で寿司や天ぷらが食べ放題。
味はそれなりだけど、天ぷらを食べるのはL.A.に来て初めてだったような気がする。
帰ってきて企画書書き。
朝の4時までかかってやっと一通り書き終えたけれど、まだ自分で納得できる内容じゃない。
明日もう一度読んで手を入れなければ。
午前11時起床。
去年の夏にL.A.を離れたNobuが遊びに来ているというので仲間が集まってチャイナタウンで飲茶。
チャイナタウンは旧正月ということでパレードでにぎわっていた。
テレビで中継していたサンフランシスコのチャイナタウンよりは地味だけれど、それなりの雰囲気。
打楽器にあわせて獅子舞らしきものが練り歩いていた。
大人数集まった時の飲茶はやっぱり楽しい。
お腹いっぱい食べて1人たったの$7。
日本でこの値段じゃ絶対食べられないよなぁ。
食後、Nobuたちはガンを撃ちに行ったけれど、僕は山盛りの宿題があるのでまっすぐ帰宅。
企画書に手を入れてメールで送り、テキストのリーディング。
55ページ中、まだたったの8ページ。
今日も徹夜になりそうだ。












