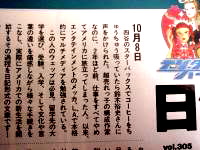|
|
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|
2 掲示板 |
|
掲示板 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
|
|
5月 6月 7月 8月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 3 4 |
|
|
|
|
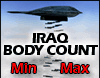 |


語学学校99年秋5
(1999年11月1日〜)
| 11月1日(月) |
| いつものように語学学校へ。 今週から台湾人と日本人のクラスメイトが1人ずつ増えた。 会話のクラスでキング牧師と黒人運動についてのテープを聞く。 面白かったのは先生の余談。 アメリカ史の本を読んで、僕もこの人権史について考えたことがあった。 日本にいたときは「差別」と言われてもピンとこなかったけれど、ここアメリカではマイノリティーであることが身にしみる。 最近、どこかで読んだ文章の中に「国際感覚とは世界の中での自分のポジションを客観的に位置づけられることだ」というのがあった。 授業の後、日系書店を3軒はしごして、やっと「SPA!」最新号(11月3日号)を入手。 渡辺浩弐さん連載の「バーチャリアン日記」(160ページ)。 ここまで書いて突然、既視感に襲われた。
ハッカーたちがなぜLInuxなどオープンソース・ソフトのプログラミングに積極的に関わるのか、その動機を説明した部分。 |
| 11月2日(火) |
| 睡眠時間もたっぷり。 ばっちり体調を整えてUCLA Extensionへ。 「Fundamentals of New Media for the Entertainment Professional」2回目の授業だ。 今日のゲストスピーカーはEMI Recorded MusicのSenior Vice President、Jay Samit氏。 そんな彼が現在、音楽業界に身を置いているのは「回線速度の関係で映像ビジネスより音声ビジネスの方が先に革命に見舞われるから」だとか。 ところが、である。 いや、聞き取れないというのは正確じゃない。 なぜだ!? かろうじて聞き取れた部分だけ、必死でノートをとる。
2時間半のレクチャーと質疑応答で理解できたのはたったこれだけ。 いつか英語がばっちりになったらもう一度しっかり聞いてみたい授業だ。 |
| 11月3日(水) |
| 昨夜は日記更新のあとチャットしてしまったが、なんとか宿題もやって語学学校へ。 UCLA Extensionの授業で英語が聞き取れなかったショックをひきずりつつも、「これを乗り越えるためにはとにかく勉強するしかないんだ」と気合いを入れて教室に向かう。 文法、リーディングに続く会話のクラスでKeith先生が言った。 授業の前半でクイズは終了。 「minister」の意味を答えるように指名された僕はこう言った。 すると、先生は意外なことを言った。 え〜っ、そんなことないんじゃないの? 僕がそう主張すると、先生は少しムキになってこんなことを言う。 カッチ〜〜〜ン! 必死で主張する僕を先生はサラッと流して次の問題へ。 怒りが収まらない僕は、授業の最後にもうひとつ先生に噛みついてしまった。 すると、先生は明らかに不愉快な顔になって、「ESL学生がしゃべれない最大の理由はボキャブラリー不足なんだ」という。 しつこく食い下がる僕をうるさいと思ったのか、先生は「分かった。Hiroの意見は気にとめておくよ」と言い残して教室を出ていった。 あ〜あ、気分は最悪。 |
| 11月4日(木) |
| 今年5月にテレビ朝日「トゥナイト2」のE3取材の時にコーディネーションでお世話になったKokoさんが「ご飯でも一緒に食べませんか? 紹介したい友だちもいるし」と声をかけて下さった。 Kokoさんとは先日、工藤夕貴さんとの食事会の時にばったり再会し、「L.A.の日系メディア業界は狭いね」とメールアドレスを交換していたのだ。 我が家からほど近いソーテルのNijiya前で待ち合わせし、居酒屋「風来坊」へ。 びっくりしたのはAさんが僕のホームページを読んで下さっていて、以前に一度メール交換もしていたということ。 このAさんのお話が僕にとってはとても刺激的だった。 インターネットの普及はおそらくクリエイターの仕事のやり方を大きく変えるだろう。 音楽業界ではすでにアーティストとユーザーが直接つながる動きが始まっているけれど、データ回線の拡張に伴って映像業界も本格的に動き出すだろう。 ところで、昨日の語学学校での「事件」についてたくさんのメールや掲示板への書き込みをいただきました。 |
| 11月5日(金) |
| 毎週顔を出しているCSUNのCoffee Hourをパスして語学学校へ。 というのも、以前にこのホームページを通じて知り合ったいけしたゆうじさんが授業を見学にくるからだ。 いけしたさんは映画のバイリンガルシナリオを出版しているスクリーンプレイ出版で5年間編集長をつとめた後、今年6月からCalifornia State University, fullertonの大学院でTESOL(英語教授法)を専攻しているという、いわば英語教育の専門家。 ESLのクラスを見学し、それを15ページ(!)のレポートにまとめるという課題があるのだそうだ。 知人、しかも英語のプロに見られているというので少し緊張気味だったけれど、今さらとりつくろっても仕方がない。 まずは「『スィー』と『シー』の発音がゴッチャになっているから気をつけた方がいい」。 そして「言いたいことを正確に伝えるためにライティングの機会を作った方がいい」。 授業の後、Mさんを誘って3人で食事。 コミュニケーションの手段としての言語ではなく、受験問題を解くための技術を教えざるを得ない現場の実状。 「せっかくお2人にお会いするのでネタを用意してきました」と、いけしたさんがカバンから取り出した紙にはこんな一文がプリントされていた。
「これを声に出して読んでみて下さい。『f』の音は全部でいくつありますか?」 |
| 11月6日(土) |
| たいした勉強をやっていないとはいえ、週末が来るとやはりホッとする。 たまった洗濯物をアパートのコインランドリーに突っ込み、部屋の掃除。 それから「FRIENDS」のビデオを繰り返し見る。 午後、Kojunが来て「Inside Edition」のビデオチェック。 夕方から勝治が遊びに来ることになっていたのだけれど、急に予定が変更になってキャンセル。 「声」の文化から「文字」の文化へ。 さあ、それではここで昨日の問題の正解です。
『f』の音は全部で6つ。 なぁ〜んだ、そんなの当たり前じゃん、というなかれ。 ネイティブがこの文を読むと、リダクションが起こって「of」の「f」の音が落ちてしまうのです。
となるから『f』の音は3つになってしまうというわけ。 |
| 11月7日(日) |
| 昼頃起きてのんびりテレビを見る。
15分おきにトップニュースを繰り返す(少しずつ更新されてはいる)CNNのHeadline Newsチャンネルを見るも、なんだかうまく聞き取れない。 「デジタルメディアは何をもたらすのか」(有馬哲夫・著/国文社)読了。
技術の進化がメディアを変化させ、それは人間のリテラシーやメンタリティーに影響を及ぼす。 著者はまた、このパラダイムシフトに伴う衝突(conflict)にも言及している。
テレビに親しんだ僕らにとっては笑い話にしか聞こえないけれど、同じことがデジタルメディアについても言えないだろうか。新しいメディアの特質に目をつぶり、既存のメディアの手法でしかインターネットに触れることができないのなら、僕らは彼らを笑えない。 この新しいメディアは何をどう変えるのか?
|