|
|
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|
2 掲示板 |
|
掲示板 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
|
|
5月 6月 7月 8月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 3 4 |
|
|
|
|
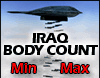 |


「Los Angeles 留学日記」
大学院99年春2
(1999年2月10日〜)
2月10日(木)
午前9時起床で学校へ。
Computer for New Mediaの授業だ。
前半は「Object」「Event」という語の概念について。
実際にフローチャートを描きながら説明してくれるのでなかなか分かりやすい。
後半はLingoスクリプトを使ったDirectorムービーの制御方法の実践。
テキスト付属CD-ROMに収録されたムービーを教授の指示に従って少しずつ書き換えていくのだ。
これは楽しくてハマりそうだ。
今学期初めて教室のMacを使って気づいたのだが、インストール済みのソフトがかなりアップグレードされている。
MacOSが8.5になっているのはもちろん、PhotoshopとPremiereは5.0、Illustratorは7.0、MS Officeはしっかり98になっていた。
使い勝手が向上したり安定感が増したりするのは大歓迎だけれど、手持ちのソフトとバージョンが離れてしまうと自宅で作業がしにくくなってしまうから痛しかゆしだ。
第一、日本語版のマニュアル本が追いつかなくなってしまう。
授業の最後に来週締切のWritten Assignmentの課題が発表された。
みんなが身構えているとGotthoffer教授がニヤッと笑ってひとこと「Do the Game!」。
へっ? ゲームをやれ????
聞き間違いかと思ったらそうではなかった。
何でもいいからコンピュータ用のCD-ROMゲームをやり、その中の一場面についてフローチャートを描いてこいというのが課題なのだ。
うん、なかなか面白そうじゃないか。
何のゲームをやろうかな?
続いて丸2ヶ月ぶりのEnglish Conversation Class。
掲示板にも書き込んでくれたSebastian、Katuji、Tomoyoちゃんといった先学期からの顔見知りに加え、新顔が7〜8人。
中国や韓国、タイといったアジアからの留学生が多い。
ほとんどがアメリカに到着したばかりという新入生だ。
そうか、新学期なんだよなぁ。
自己紹介の後、「インターネットに載せるから写真を撮らせてくれ」とお願いしたらみんな大歓迎。
「日本語は読めないけど写真は見れるからURLを教えてくれ」という会話で一気に場がなごんだのだった。
こんな小さくちゃ誰が誰だか分からないかな。
インストラクターのRoopaさんを中心に話していると、中国人の新入生が「ごめんなさい。よく聞き取れないのでもっとゆっくりしゃべってくれませんか」と一言。
それを聞いて数ヶ月前の自分を思い出した。
僕が初めてこのクラスに来たときも確かにRoopaさんの英語がよく聞き取れなかった。
きっと中国人の彼はあの頃の僕と同じに違いない。
逆に言えばこの数ヶ月の間に僕の耳が進歩したということだ。
うむ、継続は力なり、かも。
アパートに帰ると篠原さんから留守電が入っていた。
メシでも食いに行きませんか、というお誘いだ。
そう、Santa Monica College組は今日冬学期のファイナルの最終日。
打ち上げといえばもちろんKorea Townだ(笑)。
ここ2日間ほとんど寝てないというKojun、大食漢のKenと一緒にフリーウェイを東へ向かう。
今日の店はKorea Townの中心から少しはずれところにあるPure Luckというチャイニーズコリアン・レストラン。
篠原さんが韓国人の同級生に教えてもらったという。
外観はすだれのかかった海の家風でさびれた感じ。
そんなに治安の良いエリアでもないし、日本人観光客はまず来ないところだ。
味はそれほどでもないけれど、この店がすごいのはなんと言ってもボリューム!
全てのメニューが普通の店の2〜3倍の量。
それでいてお値段は各$7〜8というから、「これで儲けあるの?」なんて余計な心配までしてしまうほどだ。
しかも、なかなかいけるチャーハンがおかわり自由というのも嬉しい。
4人で4皿頼んだ僕らは当然全部食べきれるはずもなく、大食漢のKenも「参りました」とギブアップ。
各自が残り物を持ち帰り用の箱に詰め込んでテイクアウト。
これだけでもう一食はいける。
「チャーハンもっと要る?」という店員さんの申し出を僕らは丁重にお断りしたのだった。
2月12日(金)
午前5時起床。
今日は、いつも大変お世話になっている篠原さんの誕生日。
Kojunたちと相談した結果、オリジナル石狩鍋で盛大に祝おうということになり、早朝のダウンタウンへ車を走らせる。
目指すは魚市場。
VictorvilleでSAKURA-YAというグロッサリーを経営するNorikoさんの買い出しに便乗させてもらうのだ。
朝一番の魚市場に並んでいたのは新鮮なマグロ。
スーパーマーケットに置いてあるのとはひと味違う。
僕らが包丁職人のお兄さんにリクエストしてその場でサーモンをさばいてもらっていると、Norikoさんから篠原さんへなんとマグロのプレゼント!
Norikoさんにはいつもお世話になりっ放しでホントに頭が上がらない。
どうもありがとうございます。
一旦帰宅して魚を冷蔵庫に入れ、そのままCoffee Hourに参加すべく学校へ。
いつものようにわいわいやっていると、English Conversation ClassのインストラクターRoopaさんが近づいてきて意外な話を持ちかけてきた。
「ねぇ、私はSPICEというプログラムのコーディネーターをやってるんだけど、Hiroもスピーチで参加してみない?」
ほぇ? スパイスって何のこと?
よく話を聞いてみると、SPICEというのはStudent Panels for an International Curriculum and Educationの略。
いろいろな教授や授業のリクエストに応じて留学生が教室に出向き、パネリストとして自分の国のことをスピーチするというプログラムだそうだ。
現在、日本人のパネリスト登録はないのだが、あるクラスから日本人留学生のリクエストが来ているという。
テーマは「阪神淡路大震災」。
CSUNのあるNorthridgeは数年前のLos Angeles大震災の震源地となったということもあり、人々の地震に対する関心が深い。
そこで日本で起きた大震災についてスピーチをして欲しいということなのだ。
阪神淡路大震災といえば発生当日から数日間、生放送の特番スタッフとして関わった印象深いニュースの1つ。
アメリカ人の学生と話しながら日米の災害対応の違いについて知るのは僕にとっても有意義なことだろう。
さらにごくわずかだが授業料の補填があるというのも嬉しくないはずがない。
喜んで引き受けることにした。
どうせやるなら聞く人たちの印象に残るものをやりたい。
ということで笹生さんに被害の様子を伝える同録VTRと記録写真がないか調べてもらうことにした。
もちろん、僕のいたらないスピーチ能力を補ってもらうという意味あいも大きいのだけれど。
帰宅後、仲間が我が家に集まってきてそのまま篠原さんの誕生パーティーに突入。
これがスペシャル石狩鍋だ!
新鮮なサーモンの骨でとったダシとミソの風味がきいて、メチャクチャ旨い!
Kaoruちゃんお手製のアップルパイに立てたロウソクを吹き消す篠原さん。
35才の誕生日おめでとうございます。
四捨五入したら40才だなんて、普段の若々しい言動からは信じられませんね。
そのままみんなでワイワイ騒ぎ、今の時刻は朝の4時過ぎ。
本当に長い一日だった。
ああ、今夜はぐっすり寝るぞ!
2月13日(土)
正午起床。
我が「Los Angeles留学日記」CD-ROMのオーサリングを快く引き受けてくださったグラフィックデザイナー金子さんと今後の方針の打ち合わせをすべく部屋を訪ねる。
金子さんの家はLos Angelesでも有数の高級住宅地Marina del Reyにあり、なんとヨットハーバーに面したテラスがある。
いいなぁ。優雅だよなぁ。
こんなところに住んでいたら創作意欲がガンガン沸いてくるんだろうなぁ。
居心地が良すぎてついつい長居をしてしまった。
帰ってきて教科書のリーディング。
今週の課題範囲は19ページ。
先週の63ページに比べれば楽勝だと思うとついつい気がゆるんでしまうが、今週はフローチャートの宿題やSPICEのスピーチ準備もしなければならないのだ。
あんまり先送りしていると後で痛い目にあうぞ、と自分に言い聞かせてはみるのだけれど…。
2月14日(日)
正午起床。
スピーチを頼まれたSPICEの登録申込書を記入していたら、なんと1ページのエッセイを書けという項目を発見。
そういえばそんなことを言っていたような気がするぞ。
1 あなたはこのプログラムに貢献できるどんな経験を持っているか?
2 あなたが母国についてスピーチするにあたってどんなことを望んでいるか?
3 経済的理由以外にあなたがこのプログラムに参加することによって得られる個人的利益は何か?
うわぁ、めんどくせえ。
が、一旦引き受けたものはやらざるを得まい。
出願時のエッセイに手を加え、2時間くらいでなんとか書き上げる。
このとき初めてMicrosoft Word 98を使ったのだが、このスペル&文法チェック機能はすごい。
けっこう複雑な文法ミスに対しても実に的確な代替案を提示してくるのだ。
バージョン6.0に比べると感動的ですらある。
あまりに面白いのでわざと間違った文章を書いて、どんな風に直すか遊んでみたりして。
こりゃ、今後のエッセイ書きがずいぶん楽になるぞ。
で、やっと教科書のリーディングに取りかかる。
「情報伝達速度が格段にアップして我々は『1つのご近所(グローバルビレッジ)』の住民になった」
「情報量の拡大に伴って情報の質は玉石混淆になった」
「我々は史上初めて情報量の過剰に直面し、同時に情報に対する無力感を味わうことになった」
メディアが印刷物から電信に移行した19世紀半ばのアメリカについての描写説明だ。
今インターネットについて言われているのとほとんど同じじゃないか。
時代は繰り返すってことかな。
で、その後アメリカの電信情報社会はどうなったのか?
続きはこれから読みますです、はい。
2月15日(月)
朝までかかって課題のリーディングは終了。
夜にならないと集中力が出ないというのはなんとかしないといかんなぁ。
後半部分は電信と共に普及し始めた写真とテレビについて。
「写真を添えることによって新聞のニュースは“感覚的”なものになった」
「『海』や『森』を写真に写すことはできるが『自然』という概念は伝えられない。『真実』や『愛』も写真には写らない」
「テレビは真実の一部を切り取り独特のバイアスをかけて伝えるが、我々はそのバイアスに対して不感症になってしまった」
著者はだから書物による文化の方が優れていると言いたいようだ。
がしかし、各メディアが固有の特徴を持っているのは当たり前であって、送り手も受け手もそれを自覚しながら適材適所でメディアを使い分けるべきなのではないか。
メディアに特徴こそあれど優劣はないと僕は考えるのだけど。
午後から篠原さんが来て「Inside Edition」の翻訳作業。
そのままRisaちゃんとKanaちゃんも加わって篠原さんの宿題をお手伝いする。
今回の課題は「照明」。
学校から借りてきた機材を使い、照明の組み合わせによって対象物がどう見えるか検証するというものだ。
さすが映画学科だけあって1000ワットもある本格的な照明機材が3つ。
照明については僕も先学期に勉強したけれど、あくまで机上の論理だけだったので、それを目の当たりにできるのはいい経験だ。
これに限らずアメリカの大学というのは卒業後の実務に直接結びつく部分を重要視するように思える。
日本の会社における新入社員研修の部分を大学が担っているのだろう。
どちらが優れたシステムかは簡単に結論を出せないけれど、学生のモチベーションを高めるという意味ではアメリカの方が効果的だと思う。
さて、明日は学校。
予習はばっちりだけど、どこまでディスカッションに参加できるかな。
午前7時起床。
授業はいつも通り11時からだが、その前にInternational Student OfficeにSPICEの書類を提出しなければならないため、早めに家を出る。
本当は30分もあれば十分だけれど10時半では駐車場が確実に満車だから仕方なく9時に到着。
あ〜あ、また寝不足だ。
オフィスではRoopaさんが僕を待ちかまえていた。
地震については3件も要望が来るとのこと。
とりあえず3月5日を本番として、その前に日時を決めてリハーサルを行うことにした。
「今、日本のテレビ関係者に阪神大震災のVTRを探してもらっています」というと、「それはぜひ見たいわ」とかなり期待している様子。
ということなんで、笹生さん、ぜひよろしくお願いしますね(笑)。
授業までカフェテリアで時間をつぶしてNew Direction in Electronic Mediaの教室へ。
教授が今日のディスカッションを切り出す前に1人のクラスメイトがこう言った。
「テキストの中ではテレビがボロクソに言われてますが、私たちはそんなに希望のない職業に就くために勉強してるんですか?」
なるほど。
僕はもちろんテレビの良いところも悪いところも相対化して冷静に読んでいたけれど、これからテレビ制作の仕事に就こうという学生には気になるところなんだろう。
この一言をきっかけにクラス全体を巻き込んだディスカッションが始まった。
「大学の授業とは何か?」「キャリア教育の意義は?」から始まって、「メディアとは何か?」果ては「幸せとは何か?」まで実に2時間に及ぶディスカッション。
なかなか興味深い内容なのだけれど、僕はなんとか流れについていくだけで精一杯。
自分の意見を言おうとした瞬間に議論は次のトピックに移ってしまっている。
僕がよほど何か言いたそうな顔をしていたのだろう、教授が流れを止めて「HIro、日本ではこれはどうなってるんだ?」と助け船を出してくれたてやっと発言できるというありさま。
しかも、直前の発言が聞き取れていなかったので「質問の要点をもう一度お願いします」と聞き直してから答えるという体たらくだ。
はぁ、情けない。
言いたいことがあるのに言えないというのはかなりストレスがたまる。
もし同じディスカッションが日本語で行われていたらいくらでも語ってやるのになぁ。
後半は「テレビ」と「書籍」のメディア特性の違いについてのディスカッション。
「リサーチペーパーを書くときに書籍で調べるのとテレビで調べるのでは何が違うか?」という教授の質問に対してみんなが口々に意見を言い合う。
書籍だとめんどくさい、時間がかかる、イライラする、といった否定的なものが代表意見。
一方テレビは楽だ、面白い、便利だという肯定的な意見が多い。
ひねくれ者の僕が「テレビは繰り返しできない」とあえてネガティブな見方を出すと「だったらビデオに録画すればいいじゃん」だと。
アメリカの若者もみんなテレビが好きなんだなぁ。
またもや脳みそがウニのようになっていると、あっという間に時間終了。
どうしてもタイミングがつかめずに言えないことがあったので授業後、教授のところに行って一言。
「でも、1時間のドキュメンタリー番組を作るのにスタッフは数十冊の資料を読むんですよ」
すると教授は「それは面白い意見だ。ぜひディスカッションの間に出してもらいたかったよ」。
だから、それが言えなかったんだって(泣)。
授業の後一服していると、先学期のクラスで一緒だったTheoが声をかけてきた。
今日もし時間があったらRTVF341「Video Production snd Editing」の実習を手伝って欲しいという。
「いいよ」と軽く返事をしたら、なんとミニドラマに出演してくれというのだ。
「英語のセリフはしゃべれないよ」と釘をさしたら「セリフはないから大丈夫」と笑う。
約束の時間に指定場所の教室を訪ねると、全く面識のない外人(当たり前だ!)が10人ほど集まっていた。
説明によるとこれは学園ドラマで僕は宿題をいっぱい出す意地悪な教授の役なのだという。
カメラは1台だけだけど、モニターや照明などはちょっとしたロケ番組に負けないほどの機材。
CSUNのテレビ制作学科は機材が充実しているというのは本当らしい。
ディレクター役の学生の指示に従って撮影はスムーズに進む。
時々英語の指示が分からなかったりするけれと、それはそれでご愛敬だ。
当たり前だけど本当に「アクショ〜〜〜ン!」「カ〜〜〜ット!」っていうんだなぁ(笑)。
自分の出番がない時はデジカメを持って逆取材。
「インターネットに載せたいんだ」と言うと「今晩絶対チェックするからURLを教えて!」攻撃を浴びる。
というわけで、メチャクチャ眠いのに頑張って更新しているのでありました。
午前9時、Roopaさんからの電話で叩き起こされる。
どうやらSPICEの登録をするのに僕が今学期6単位しか取っていないのが問題らしい。
(留学生はステイタスを維持するのに学部生12単位、院生8単位を履修しなければならない)
取りたいのに取れないPrerequisite事情を説明すると、学部事務所に行ってその事情を確認する手紙を書いてもらってこいとのこと。
そこまでしなきゃいけないのはめんどくさいけれど、乗りかかった船だからしょうがない。
明日事務所に行くことにしよう。
朝食の後たまっていたメールに返事を書き、Computer for New Mediaの宿題に取りかかる。
ゲームをやってそのフローチャートを描けというのがその課題。
今さら新しいゲームを買うのももったいないので、手持ちの「上海」というパズルゲームを題材に選ぶ。
これは積み重なった麻雀牌の中から同じ種類をクリックして消すだけというシンプルなパズルゲーム。
だが、フローチャートにするとなるとなかなか複雑だ。
「牌の上でクリックイベント発生」→「すでに反転している牌が他にある?」の後、
YESなら「その牌の最低2辺が他の牌と接していない?」という選択肢に進み、
さらにYESなら「その牌はすでに反転している牌と同じ種類?」
さらにYESという条件を満たしてはじめて「反転する」→「ダブルクリックイベント発生」→「消去」となり、
やっと1組の牌を消すことができるのだ。
もちろんそれぞれに「NO」のチャートも付けていく。
なんだか設計図を見ながらプラモデルを組み立てていくような感覚。
もちろんそれはゲーム本体があるからであって、もし自分でゼロからゲームを作るとしたら全く違う感覚になるんだろうな。
思ったより早くできたのでチャートを見やすく色分けなんかしてプリンターで印刷。
おおっ、バッチリだぜ。
午前9時起床で学校へ。
久々に6時間くらい寝たので目覚めもいい感じだ。
Computer for New Mediaの授業は引き続きLingoというスクリプト言語の解説と実践。
先学期のFinal Projectでも一緒だったJamesとチームを組む。
見た目の通りさわやかな彼はマルチメディアと同時に社会学を専攻する好青年。
英語が不自由な僕の「えっ、今なんて言ったの?」攻撃にもいやな顔ひとつせず、とことんつきあってくれるいいヤツだ。
Gotthoffer教授が作ってきた簡単なDirectorムービーを自分たちなりに分析し、どうやったらそんな動きが実現できるのか2人で試行錯誤。
まだまだLingoの知識が足りないのでテキストと首っ引きでやるしかない。
今週末は集中してマニュアル本を勉強しなくては。
授業の最後に18ページのゲーム企画書(書式から想像するにGotthoffer教授が博士課程の論文として提出したもののようだ)が配られる。
来月締切のCD-ROMプロジェクトはこれがベースになるようなのでしっかり読んでおかなければなるまい。
続いてEnglish Conversation Class。
今日一番面白かったのはイランから来た女の子の「母国では宗教上の理由で肌を露出してはいけない」という話。
白装束で全身を包んだイスラム女性の映像はテレビでよく見るけれど、家にいるときもあの格好なのだろうか?
答えは「そんなことないわ。あれは公の場所でだけ。部屋ではわりとくつろいだ格好もしてるのよ」とのこと。
ちなみに今日の彼女はジーンズにトレーナーというカジュアルな服装だった。
帰り際にSPICEへの手紙を書いてもらうために学部事務所へ。
用件を説明すると、学部長と話すよう言われ、そのまま部屋に通された。
Radio-TV-Film学部の学部長はDr. Judy Marlaneさんという女性だった。
「Mass Communication500の授業が今学期キャンセルされているのがネックで他の院の授業が取れず、やむなく学部の授業を2コマだけ履修しているんです」
「他に興味のあるクラスはないの?」
「できればマルチメディア関連の科目に集中したいんです」
「手紙はいつまでに欲しいの?」
「As soon as possible」
すると彼女は突然隣の部屋に行き、秘書らしき人に向かってブツブツしゃべっている。
2〜3分後、戻ってきた彼女の手にはなんと手紙が。
「この手紙で大丈夫だと思うわ」
そう、彼女の“ブツブツ”は口述筆記だったのだ。
しゃべるだけで手紙が書けてしまうなんて、さすが学部長(笑)。
そこで彼女から思わぬ言葉が。
「Radio-TV-Film学部は来学期以降マルチメディア関係の授業を大幅に増やす予定よ。今のままじゃコンピュータが足りないから新しい校舎も建てるつもりだし。あなたにとっても朗報じゃないかしら」
おおっ、そりゃあスゴイ!
「院にもマルチメディアの授業が増えますか?」と聞くと、「ぜひそうしたいと思ってるわ。Gotthoffer教授のように優秀な教授が必要ね」。
さらに「400番台(4年生以上の履修科目)のクラスなら院の卒業単位に算定されるから決して無駄にはならないわ。安心して」とのお答え。
なんだか目の前が急に明るくなってきたような気がする。
それだけL.A.ではマルチメディアを勉強した学生のニーズが高いのだろう。
これならトランスファーしなくても済むかもしれないぞ。
午前11時起床。
Coffee Hourに参加すべく学校へ。
なんだか最近、時間が過ぎるのがとても早い。
先週のCoffee Hourがつい昨日のことのようだ。
今日のCoffee Hourには「Sundial」というCSUNの学生新聞(?)が取材に来ていて留学生たちの写真を撮っていた。
Roopaさんを見つけたので、昨日学部長からもらった手紙を手渡す。
「これで大丈夫。さっそくサインアップしましょう」
International Student Officeにはってあるたくさんの要望書の中から彼女がピックアップしたのは環境地質学の授業だった。
求められているスピーチはこの3つ。
1 あなたの国の地震の歴史と危険性の概要
2 地震による被害を減らすために政府または市民が行っている努力
3 人々が地震の危険性を理解し心構えを持つために行われている教育的努力
阪神淡路大震災を例に挙げて日本が地震国であることを説明した上で具体的な災害訓練やボランティアの話をすればいいかな。
政府の許認可という意味では免震建築や地震保険についても面白いネタがあるかもしれない。
いずれにしても来週水曜日のリハーサルまでにインターネットで少し調べなきゃいけないなぁ。
ああ、今週末は“やらねばリスト”がいっぱいだ。
- RTVF315のテキスト読み15ページ
- RTVF461のDirector練習
- RTVF461のゲーム企画書読み18ページ
- SPICEスピーチの調査&原稿作り
ふぅ、大変だぞ、こりゃ。
















