|
|
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|
2 掲示板 |
|
掲示板 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
|
|
5月 6月 7月 8月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 3 4 |
|
|
|
|
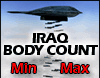 |


| 10月28日(月)〜11月3日(日) |
| 最近読んで印象深かった本を2冊。
「日本文化の模倣と創造?オリジナリティとは何か」(山田 奨治・著/角川書店) テレビやラジオの企画はもちろん、その他の仕事でも、クリエイティブと名の付く作業では常に「オリジナル」が求められるし、僕らはいつも「これまでになかった新しいもの」を創らなくてはというプレッシャーの下で頑張っている。 この本で著者は「類似性とはなにか」「模倣が中心だった西洋美術」「著作権の発祥」「連歌や本歌取りと日本文化の特徴」といった観点からオリジナルの価値を考察し、「独創」に代わって「再創」という価値観を提示している。
オリジナルと寸分違わないコピーが簡単にできるデジタル時代になんらかの示唆を与える提案だと思う。 「これまでのビジネスのやり方は終わりだ」(リック レバイン、クリストファー ロック他 ・著/倉骨 彰・訳/日本経済新聞社) 先日読んだ「ゴンゾー・マーケティング」(クリストファー ロック・著/山形 浩生・訳/翔泳社)の著者も参加した、インターネットにおける企業コミュニケーションの問題点を指摘した本。 いわゆる企業ホームページに載っている公式コメントやメッセージは消費者の心に届いていないのではないかという問題提起はまったく賛同できる。 「みなさんのご意見、ご感想をおハガキでお寄せ下さい」的なコミュニケーションはすでに死んでしまったのだ。 これ、日記才人(にっきさいと)の登録ボタンです。いつもその1票に励まされてます。 |
Previous
 Next
Next