|
|
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|
2 掲示板 |
|
掲示板 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
|
|
5月 6月 7月 8月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 3 4 |
|
|
|
|
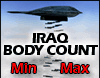 |


| 3月3日(金) |
| CSUNのCoffee Hourへ。 今日のスポンサーは日本語学科ということで寿司がふるまわれる。 コンビニの寿司みたいなものだが、寿司はやっぱり寿司。 こんなタダメシにありつけるんだからありがたい。 なぜスポンサーが日本語学科なのかというと、今学期のLanguage Exchangeのスケジュールが決まったから。 帰宅して読書。 発行が古く(1997年10月)タイトルが俗なので後回しにしていたのだけれど、これがなかなか面白かった。
この他、プライバシーと参加者利便の両面を持つ個人情報管理やブランディングの重要性など、今まさに議論になっている問題をきちんと論じているのもいい。 印象に残ったのはインプレス社長・塚本慶一氏の「日本におけるバーチャルコミュニティーの原点はニフティーの『フォーラム』にある」という記述。 なんだかちょっとおセンチな気分なのは、ここからダウンロードしてきたこの曲がBGMに流れているからか。 これ、日記才人(にっきさいと)の登録ボタンです。いつもその1票に励まされてます。 |