|
|
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|
2 掲示板 |
|
掲示板 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
|
|
5月 6月 7月 8月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 3 4 |
|
|
|
|
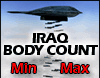 |


| 9月4日(木) |
| 相変わらず読書三昧の日々は続いている。
「テレビゲーム文化論?インタラクティブ・メディアのゆくえ」(桝山 寛・著/講談社現代新書) メディア・プロデューサーの著者が、テレビゲームの社会に対する影響を考察した評論集。
少年犯罪が起きるたびに「テレビゲームの悪影響だ!」とわめく“良識派”にこそ読んでもらいたい本だ。 「デジタルを哲学する」(黒崎 政男・著/PHP新書) 哲学者である著者がインターネットなどデジタル情報社会を“アナログな立場”から考察した評論集。 「立花隆秘書日記」(佐々木 千賀子・著/ポプラ社) その名の通り、“知の巨人”立花隆氏の秘書を5年間務めた著者が立花氏の日常を振り返ってまとめた本。 これ、日記才人(にっきさいと)の登録ボタンです。いつもその1票に励まされてます。 |
Previous
 Next
Next