|
|
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|
2 掲示板 |
|
掲示板 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|
|
2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
|
|
5月 6月 7月 8月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 3 4 |
|
|
|
|
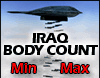 |


| 11月16日(日) |
| シネマスクランブルのプレゼンはとりあえず無事終了。 「なによりも直接ビジネスに結びつく企画を優先して欲しい」という厳しいリクエストはあったものの、そこまではっきりしてもらえたほうがこちらとしてもやりやすい。 頑張っていきましょ。 「ネットは新聞を殺すのか−変貌するマスメディア」(国際社会経済研究所、青木 目照、湯川 鶴章・編/NTT出版)読了。 日本でも最近盛り上がり始めてきた「ブログ」や、「2ちゃんねる」のような個人による情報発信が「草の根ジャーナリズム」として確立すると既存のメディアにどんな影響を及ぼすのかという問題意識を様々な角度から検証した本。 本書でも既存のメディア(特に新聞)が現在のままで生き残る可能性には疑問を投げかけている。 「大崩壊の時代(上)」「大崩壊の時代(下)」(フランシス・フクヤマ・著/鈴木 主税・訳/早川書房)読了。 工業化社会から情報化社会への変化とは何がどう変わっているのか? これ、日記才人(にっきさいと)の登録ボタンです。いつもその1票に励まされてます。 |
Previous
 Next
Next